|
| 「十字路2006」 No.5 |
|
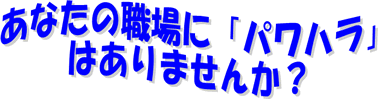 |
|
|
|
|
|
パワーハラスメントという言葉を聞いたことがありますか?
略してパワハラなどと呼ばれることもあります。
パワー、つまり仕事上の権力を不当に利用することによる嫌がらせ・いじめなどを指す言葉です。
|
パワーハラスメントはなぜ起こる?
本来、上司・部下といった関係はあくまでビジネスの上での契約で、これが人間的に上とか下とかいう事にはなりません。
しかし、いつも命令している立場にある人はこれを忘れがちになり、人間性を否定するような言動があったり、仕事上の権限を超えて命令をしたりする場合があります。これがパワーハラスメントの原因になる事が多いのです。
こんな場合はパワーハラスメント?
パワーハラスメントとしてよくある事例を挙げてみましょう。
強制的に飲み会などに付き合わされる
就業時間以外の行動を束縛するのは不当な権力行使に当たります。誘いを断った時に不利な扱いを受けた場合も同様です。
頻繁に大声で怒鳴りつけられる
仕事上の指導であっても頻繁に怒鳴りつけたり、過剰にストレスを与えるような言動はパワーハラスメントになります。
「辞めれば?」などと言われる
これは典型的なパワーハラスメントの例です。精神的に追い込んで辞職させるような行為は許されません。
仕事の内容を事細かにチェックされる
これは微妙な所ですが、他の労働者と比べて明らかに酷い場合は完全にパワーハラスメントになります。
殴られたり、物を投げつけられる
このような場合はパワーハラスメント以前に傷害罪などの犯罪行為になります。
権限を越えた命令・指導=パワーハラスメント
先日開催された県教研の「職場の民主化」分科会には、学校でのパワーハラスメントの実態が多く寄せられました。以下にその一部を紹介します。
意のままに動かない職員はゆるせず、評価制度自己申告後の面談で異を唱えた先生を怒鳴る。合同の学年部会が「3・4年」「5・6年」の組み合わせでないとゆるせない?らしく、運動会で合同種目のある「4・5年」の担任が打ち合わせをしていたことに怒鳴る。
校長は感情の起伏が激しく気持ちが高ぶると涙を流して、いわゆる「きれた症状」になり、ときに机に物を投げつけ相手を罵倒する。全校集会の児童生徒の発表の際、「読み方が悪い。声が聞こえない。聞いているとストレスがたまる」と髪の毛をかきむしりながら怒鳴り、職員が抗議すれば「ときには人の前で恥をかかせることも必要」などと開き直る。この校長は女性だが、地域の転入職員の歓迎会の場で、女性職員にお酌をして挨拶に回れと強要し、それが常識だと言う。水泳やシーカヤックの練習の際、若い男性教師の体をさわる。まとわりついて離れない。
ちょっと信じられませんが、鹿児島県内で実際に起こったことであり、こうした学校では、ストレスで体調不良を訴える職員が続出しています。
そんなとき、どうすればよいのでしょうか?
何よりも大事なのは自分の身を守るということです。パワハラを受けた方は、精神的に参ってしまうことが多いと思いますが、「自分はパワハラを受けている」という自覚を持ち、まずはストレスがたまらないように「ちょっと休む」「信頼できる人に相談する」「病院に行く」など具体的に精神が休まる対処法を考えるべきです。
鹿教組は、交渉等で県教委に対して学校現場からあがってくるパワーハラスメントの実態を指摘し、具体的な解決方法を要求しています。
もし、あなたがパワーハラスメントを受けていると感じているのに、どう対処したらよいかわからないときは、いつでも鹿教組(℡099-223-8345、E-mail:kjtujousencp@g-coop.com)にご相談ください。
ちなみに管理職がこのチラシを見て、配らせないだとか言うこと自体がパワハラです。あしからず。
|