|
| 問題提起!「十字路2005」 No.7 |
|
 |
|
| 「評価者の問題」編 |
|
|
|
あなたは、今年から一部試行が始まった「教職員評価制度」をどのように考えていますか?鹿教組は、大前提として「教職員の日々の教育活動を、評価するのは不可能」だと考えています。今回は「評価者=管理職」の問題に焦点をあててみました。
鹿教組では、今年度からの試行校の組合員を集めて情報交換し、実態把握をはかっています。
そこで出された事例にはこのようなものがありました。
管理職による指導が強まった事例
- 2年目の校長だが、ふだん学校行事に顔を出さない。子どもの活動を見ない。なのに評価制度の試行が始まってから、毎朝9時に巡視に来て5〜10分教室にいて子どもにも声をかける。余計なことはしないでほしい。
- NRTの平均点、県版テストの平均点、虫歯の治療率を数値目標にするよう指示があった。
- 校長教頭の指導する場、態度が強くなった。「○○をしてください。」
管理職が自分の評価を気にしていると思われる事例
- 校長が、6月から近隣によく目立つ校門付近で草とりを始めた。毎朝同じところでやっているので、今では草一本はえていない。一体何をとっているのかと職員がうわさしている。
- 教頭(今年着任)が、6月になって庭仕事を始めた。それまでは補教も加配の空き時間を全てあてようとしていた。自分はパソコンに向かっていて…
- 事務所訪問前、わざわざ自分で苗を買ってきて花を植えていた。(ふだんはしないのに…)
管理職が評価者として不適格だと思われる事例
- 評価の仕方について、校長の説明に対して質問したら「わかりません」。
- 給食係はコンテナ室にいつも行っているが、校長はのぞいたこともない。
- 自己評価で、Aと書いた人に「設定が甘い」、B・Cと書いた人に「自己評価が辛い。Aでいいんだよ」と言う。支離滅裂。
以上は、ほんの一部を紹介したに過ぎません。この他にも「人事を絡めて話題にする」や「地域行事への参加等、休日の行動まで評価しようとする」など、多くの問題があがっています。
県教委は「将来的に給料等や人事等を含めた処遇への反映を検討する」としていますが、はたして、このまま導入されてよいものでしょうか?
鹿教組は、この問題について制度導入が検討され始めた時点から、上記のような職場実態等をふまえて、拙速な導入に反対しています。
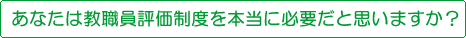
|